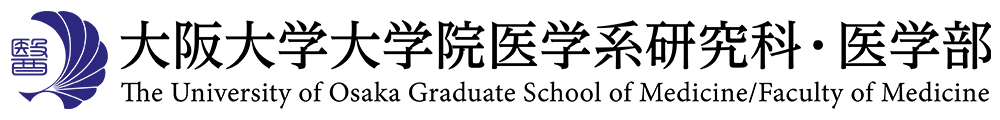最後まで残る感覚、聴覚について 保健学専攻 医療技術科学分野 機能診断科学講座(放射線画像科学) 髙島 庄太夫
医療技術科学分野 機能診断科学講座(放射線画像科学)
教授 髙島 庄太夫
今から50年以上前、私が小学高学年の時に私が医者を志す一つの契機となった出来事に出くわした。私の実家の丁度前に内科医院があったので、風邪の症状でその医院の門をくぐった。そこで一本の筋肉注射をうけその玄関を出た瞬間に嘔吐を催し、ショック状態となりその医院の診察台に倒れ込んだ。体の一部を少しでも動かすとその後にどっと大きな疲労の波がくるので、目を開けることも指一本動かすこともできなくなった。
医者は“危ないので親族縁者を呼びなさい”と言い、次々と親族や知り合いが私の枕元に集まって、“可哀想に”等々と話している会話が明瞭に聞こえた。その医者は、私の左肩に何十回も筋注を施していた事を覚えている。そうこうしている内に、少し体を動かしても最悪時ほどの疲労の波は感じなくなり、”ああ、良くなるかもしれない”と思った。
どれ程の間ベッドに横たわっていたか定かでないが、それ以後、徐々に改善し、生死の境から生還した。
この自己体験をもとに、人間のもつ五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)のうち最後まで健全に機能する感覚につき考えてみた。この中で運動機能が伴わなければ能力を発揮できない感覚がある。視覚については、まぶたを開けることもできなかったので役に立たなかった。味覚も然りで、口を開ける力は残っていなかった。嗅覚についは、虫の息のような状態であったので、十分な働きは期待できなかったと思われる。触覚については、痛みは感じなかったが、肩に注射をしているといった感覚は何となく覚えている。
最後の聴覚のみは健全にかつ十分に機能していたと記憶している。この感覚は運動機能の関与がなくともその役割を果たせる感覚と考えられる。音は、外耳道から入り、鼓膜、耳小骨、内耳、聴神経、脳幹、側頭葉と刺激が伝わる。つまり、脳血流が保たれていれば、随意的な運動機能をほぼ用いずに、機械的に容易に完遂される感覚機能であるといえる。
私はその出来事以来、医者になって心がけている事がある。瀕死の状態もしくは意識レベルの低下した患者の前では、不用意な言葉は厳に慎むようにしている。このような状態の患者さんでも、周囲の人の声とその発言内容をはっきりと覚えているからである。さて、私事であるが、父親の臨終には立ち会うことができなかったが、現在90歳をすぎでも健やかである母親の最後に当たっては、あるだけの感謝の言葉を手向けて送り出してあげたいと考えている。